こんにちは、あなたの相続(みそら税理士法人)の廣岡です。
みそら税理士法人は、大阪、名古屋、神戸、明石、姫路の皆様の相続に関するお悩みをサポートしています。
今回は、大阪にお住まいの方、または亡くなった方が大阪に住んでいた方を対象に、「相続放棄」の手続きと、大阪特有の窓口情報について詳しく解説します。
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の借金や負債を引き継がないために行う重要な手続きです。しかし、この手続きには「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があり、迅速な対応が求められます。
特に、大阪では裁判所への申述が必要ですが、その管轄(どこに申し立てるか)を間違えると、貴重な時間を浪費してしまいます。
この記事では、相続放棄の全ステップと、大阪府内での正確な窓口(家庭裁判所)の情報をまとめました。3ヶ月の期限が迫っている方は、まずこの情報で全体像を把握し、すぐに行動を始めてください。
相続放棄手続きの全体像と3つの必須条件
相続放棄とは、被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を一切相続しない意思表示をすることです。これは、家庭裁判所への「申述」という形で手続きを行います。
相続放棄の3つの必須条件
相続放棄が有効に認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 【最重要】3ヶ月の期限(熟慮期間)を守ること
- 原則として、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に申述しなければなりません。
- この期限を過ぎると、原則として相続を単純承認(全て相続すること)したとみなされてしまいます。
- 例外的に、負債があることを知らなかったなど特別な事情がある場合は、裁判所に期限の伸長(延長)を求めることも可能ですが、速やかな行動が必要です。
- 一度行うと撤回・取り消しができない
- 家庭裁判所に申述が受理された後は、原則として撤回や取り消しはできません。
- 「条件付き」や「一部のみ」の放棄はできない
「不動産はいらないが預金は欲しい」といった条件付きの放棄や、「借金だけを放棄する」といった一部の財産のみの放棄は認められません。放棄は全ての財産に対して行われます。
【大阪特化】家庭裁判所への申述:管轄と窓口
相続放棄の申述先は、全国どこでも一律に「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と定められています。
大阪府内で相続放棄を行う場合は、以下の通り、亡くなった方の住所地によって申述先が異なります。
管轄裁判所は「亡くなった方の最後の住所地」
申述先を判断するために、まずは被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍の附票を取得し、最後の住所地を確認しましょう。
大阪府内の家庭裁判所と管轄区域一覧
| 管轄裁判所 | 所在地 | 管轄区域(被相続人の最後の住所地) |
|---|---|---|
| 大阪家庭裁判所(本庁) | 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−13 TEL:06-6943-5321 | 大阪市全域 |
| 大阪家庭裁判所 堺支部 | 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町2−51 TEL:072-223-7001 | 堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡 |
| 大阪家庭裁判所 岸和田支部 | 〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4丁目27−2 TEL:072-441-6803 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉北郡、泉南郡 |
【重要】
大阪市に住んでいた場合は「大阪家庭裁判所 本庁」へ、泉佐野市に住んでいた場合は「大阪家庭裁判所 岸和田支部」へ申述する必要があります。間違った裁判所に提出すると、貴重な時間が失われるため注意してください。
相続放棄手続きのステップと必要書類
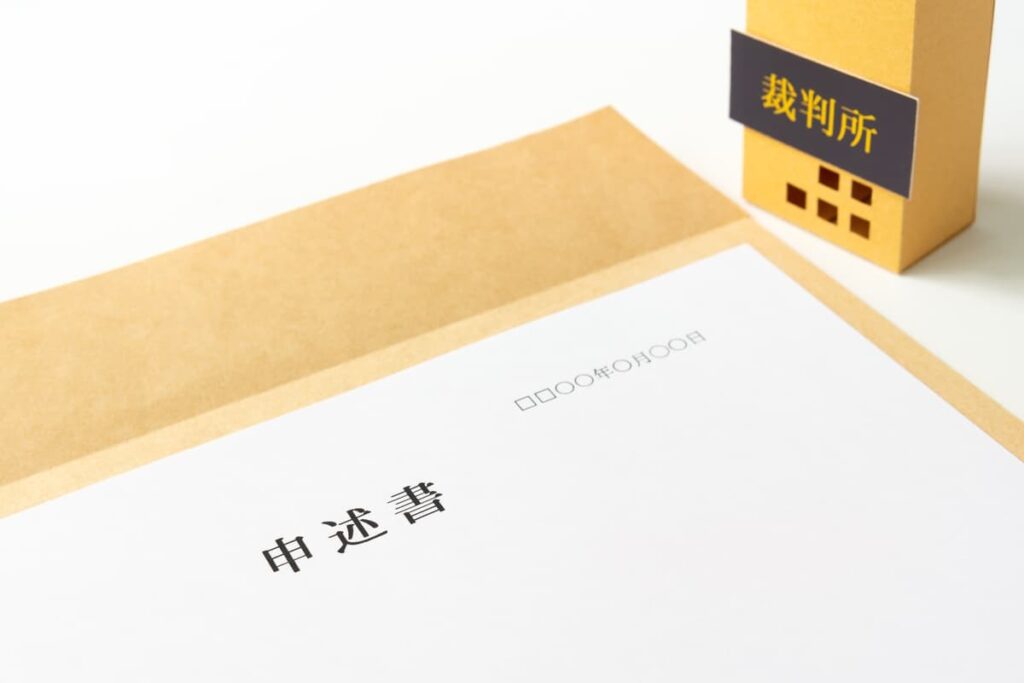
相続放棄の手続きは、以下のステップで進めます。
ステップ1:必要書類の収集
申述に必要な基本書類は以下の通りです。申述人(相続放棄をする方)と被相続人(亡くなった方)の関係性によって、追加書類が必要になります。
| 必要書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所の窓口またはホームページ | 申述理由を記載 |
| 被相続人の戸籍謄本 | 最後の本籍地の市区町村役場 | 死亡の記載のあるもの |
| 被相続人の住民票除票 または戸籍の附票 | 最後の住所地の市区町村役場 | |
| 申述人の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の市区町村役場 |
【注意】
申述人が「第二順位・第三順位の相続人(兄弟姉妹など)」である場合は、先順位の相続人がすでに放棄していることを証明する書類(先順位の相続放棄申述受理証明書など)が追加で必要になります。
ステップ2:申述書の作成・提出
- 必要書類を揃え、申述書に800円の収入印紙を貼付し、管轄の家庭裁判所に提出します。
- 書類は、裁判所の窓口に持参するか、郵送で提出することも可能です。3ヶ月の期限が迫っている場合は、郵送(特定記録や簡易書留など)の到達日を考慮して早めに送付しましょう。
ステップ3:照会書への回答と受理
- 申述後、裁判所から申述人に対し、申述内容を確認するための照会書(質問状)が送られてきます。
- 照会書に適切に回答し、裁判所が受理を決定すれば、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書が届くことで、正式に相続放棄が完了したことになります。
相続放棄にかかる費用と専門家への報酬
相続放棄手続きにかかる費用は、主に以下の実費と、専門家へ依頼した場合の報酬に分かれます。
実費(目安)
| 費用項目 | 金額(一人あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 800円 | 申述書に貼付 |
| 郵便切手代(郵券) | 数百円〜1,500円程度 | 裁判所との連絡用(大阪家裁も必要です) |
| 戸籍謄本・住民票除票などの取得費用 | 5,000円〜10,000円程度 | 取得する通数によって変動 |
| 合計 | 約6,000円〜12,500円 |
専門家(司法書士・弁護士)への報酬
専門家への報酬は、依頼する事務所や手続きの複雑さによって大きく異なります。
- 司法書士/弁護士への報酬:別途3万円〜10万円程度が相場とされています。
期限が迫っている場合や、必要書類の収集が複雑な場合(例:疎遠な親族の戸籍収集など)は、司法書士や弁護士に依頼することで、手続きをスピーディーかつ確実に進められます。
【専門家解説】相続放棄で絶対にしてはいけないNG行為(単純承認とみなされる行為)

相続放棄の手続き中に、以下の行為をしてしまうと、「法定単純承認」とみなされ、家庭裁判所に申述しても受理されなくなる可能性があります。
- 相続財産の一部または全部を処分・隠匿すること
- 預貯金の解約や、不動産・株式の売却、賃貸アパートの家賃の使い込みなど、財産価値を変える行為は全てNGです。
- 【注意】 葬儀費用を被相続人の預金から支払う行為は、金額によっては問題になることがあります。必ず専門家に相談しましょう。
- 相続財産を消費すること
- 被相続人のクレジットカードの債務を支払うことなども、一部の単純承認とみなされるリスクがあります。
- 相続財産を隠す・偽造すること
- 借金があることを隠し、一部の財産を自分のものにしようとする行為は、相続放棄が認められません。
法定単純承認とみなされると、たとえ3ヶ月以内であっても、相続放棄はできなくなります。 安易な行動は避け、不安な点があればすぐに専門家に相談してください。
みそら税理士法人が解説!相続放棄のよくある質問Q&A
Q1. 相続放棄は司法書士と行政書士どちらが頼んだほうがいいですか?
A. 司法書士または弁護士に依頼してください。
相続放棄の申述書作成や、家庭裁判所とのやり取りは、法律事務にあたるため、行政書士には依頼できません。
- 司法書士:家庭裁判所に提出する書類作成の専門家です。
- 弁護士:書類作成だけでなく、裁判所での代理人としての活動(代理申述など)も可能です。
- 税理士:申述手続き自体はできませんが、相続税の計算、全員放棄した場合の次の相続人への影響、生命保険金など「みなし相続財産」に関する助言、納税義務者の確認など、相続全体に関わる税務的なサポートが可能です。
Q2. 親族「みんなが相続放棄」をすると、何が起きる?
A. 次の順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、被相続人に配偶者と子(第一順位)がおり、全員が放棄した場合、第二順位の相続人(被相続人の父母や祖父母など直系尊属)に相続権が移ります。
第二順位も全員放棄すると、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)に相続権が移ります。
この次の相続人にも、新たな3ヶ月の熟慮期間がスタートします。
- 税理士からのアドバイス:全員放棄する場合は、負債が次の相続人に移ることを防ぐため、次の相続人にも必ずその旨を連絡する義務があります。この連絡を怠ると、予期せぬトラブルにつながるため、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
Q3. 相続放棄をしたら市役所に連絡する?
A. 原則、役所への直接の連絡は不要です。
相続放棄は家庭裁判所の手続きであり、市役所や区役所(役場)に直接届出をするものではありません。ただし、被相続人の固定資産税や住民税などの督促が来る場合があります。その際は、裁判所から交付された「相続放棄申述受理通知書」のコピーを役所の担当窓口に提出することで、ご自身が納税義務者ではないことを証明できます。
大阪の相続放棄はスピードが命!まずは専門家にご相談ください

大阪にお住まいで「相続放棄を検討している」という方は、何よりもまず3ヶ月の期限を意識して行動することが重要です。
- 「期限が迫っていてどうすればいいか分からない」
- 「必要書類が多くて挫折しそうだ」
- 「相続財産に税金や不動産の評価など複雑なものがある」
このような不安がある場合は、ぜひみそら税理士法人にご相談ください。
当法人は、大阪家庭裁判所(本庁・支部)の管轄エリアのお客様を多数サポートしており、相続全般の知識に基づいて、お客様の状況に最適な専門家(司法書士・弁護士)との連携を含めたご提案が可能です。
大阪の相続税・相続手続きに強いみそら税理士法人へ、まずはお気軽にご連絡ください。
相続税の節税は依頼する
税理士で変わります。









